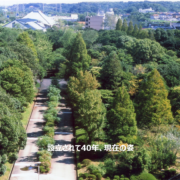高さは2~3mになり、 長い枝をのびのびと伸ばします。

アキグミ
銀色にきらきら輝く葉
特徴
葉、 枝、 実は小さな鱗状の毛に覆われてきらきらしています。 とくに葉の裏は毛が多く銀色に見えます。 この毛のおかげで、 厳しい環境でも元気に育ちます。 お菓子のグミと名前は同じですが関係はありません。
みんなの投稿
以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。
 Peak Season
Peak Season Blossom
Blossom Leaf
Leaf Fruit
Fruit
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見頃 |

|

|

|
|||||||||
| 花 |

|

|

|
|||||||||
| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|||
| 実 |

|

|

|
|||||||||
高さ
低木 (1〜5m)

|
花の性別
両性花

|
|||||||||||
分布北海道(渡島半島)、 本州、 四国、 九州、 奄美大島(徳之島まで) |
生息地河原や原野、 道端、 河岸の砂礫地などの日当たりのいい場所 |
|||||||||||
分布北海道(渡島半島)、 本州、 四国、 九州、 奄美大島(徳之島まで) |
||||||||||||
生息地河原や原野、 道端、 河岸の砂礫地などの日当たりのいい場所 |
||||||||||||
学名Elaeagnus umbellata |
||||||||||||
樹形
葉
葉の表には、 鱗状の毛がまばらに生え、 独特の感じです。
葉裏には鱗状の毛がびっしり生え、 銀白色に見えます。
花
とても強い香りがするので、 花の時期木の近くを通るだけで、 ふわっと匂います。
花は全体に鱗状の毛に生えています。
初めは白くだんだん黄色くなります。
実
実にも鱗状の毛があります。
食べられますが、 渋みがありますのでたくさんは食べられません。
場所によっては、 実がならない木が多いです。 。
幹・枝
若い枝にはやはり鱗状の毛があり、 キラキラしています。
枝によっては長いトゲがあります。 触る時は気をつけてください。
冬芽・葉痕
冬芽もやはり鱗状の毛におおわれています。
枝の先端には、 長さ5㎜ほどの冬芽が付きます。 それよりも小さな冬芽が枝の側面に付きます。
人との関わり
グミの仲間の木は材のきめが細かいので、 日常生活の道具として使われていました。 アキグミの材は手触りが良く、 道具の取っ手に使われていました。
名前の由来
方言名に「グイミ」がという言葉があります。 グイはトゲのこと、 ミは実のことをさし、 これが縮まってグミとなったという説があります。
また、 グミの仲間の名前は、 多くの場合、 果実が熟す時期が付きます。 アキグミは秋に果実が熟します。
その他の情報
日本在来種ですが、 北アメリカにも渡り、 分布を拡大しているようです。
性格
根は細菌と協力していて、 細菌が空気中のチッソから肥料を作ってくれるので最強です(逆に肥料はやらないほうがいいです)。 場所を選ばず元気に育つことができます。 暑さや乾燥にも強いので、 造成地や道路の土留めなど人工的な環境を緑にするのに植えられたりします。
体験・遊び
アキグミの実はとても渋いので、 カキの渋抜きと同じように渋抜きをしたらどうなるか実験してみよう!
ジップ付きの袋に実を平らに並べて、 焼酎をしみこませたキッチンペーパーを実の上にのせ、 ジップします。 渋みの変化を調べるためにちょっとかじって確認してみましょう。 3~4日で渋は抜け、 強い渋みはなくなり食べられます。 でも、 渋みでわからなかった違うまずさ?が感じられるようになり、 そんなにうまい話ではありません。
とはいえ、 ジャムにすると普通に美味しく食べられます。 レモンを加えるのがおすすめ。
関わりが深い生き物
花の香りに誘われてやって来たハナバチの仲間が受粉を手伝います。 他に花にはハナムグリなどの甲虫、 ハナアブ、 チョウなどの昆虫がやって来ます。 赤い実は鳥たちのごちそう。 メジロなどいろいろな鳥が食べに来ます。
タップすると詳細が見られます
見られる場所
執筆協力 : 広畠真知子、 岩谷美苗