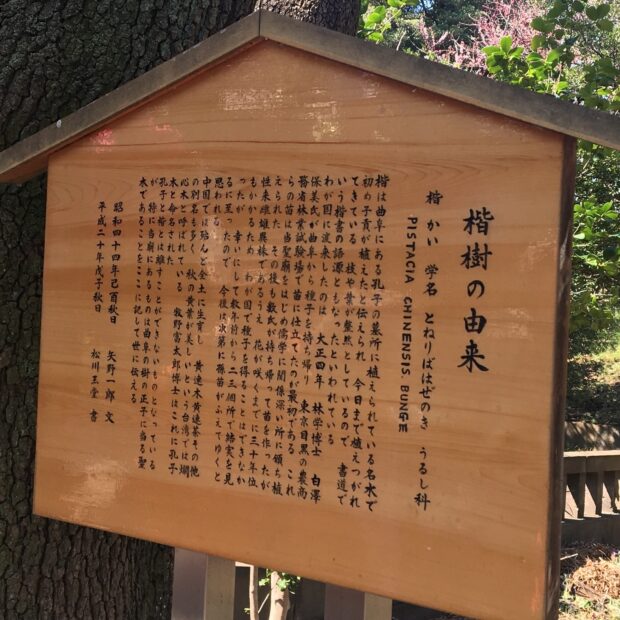成長するとほどに整った美しい形になります。

カイノキ
葉の形がきっちり、 学問の木
特徴
中国で学問の祖ともされる孔子の墓に植えられ「学問の聖木」とされてきました。
葉や枝の形や付き方が整然と整っていることが楷書(かいしょ=一画ずつ筆を離して書くきっちりした感じの字体)の特徴に似ているということで楷書の木→楷の木(カイノキ)となりました。
枝や葉などは防虫剤のような香りがします。 ウルシの仲間で、 特にピスタチオに近い仲間です。
みんなの投稿
以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。
 Peak Season
Peak Season Blossom
Blossom Leaf
Leaf Fruit
Fruit
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見頃 |

|

|
||||||||||
| 花 |

|
|||||||||||
| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|
||||
| 実 |

|

|
||||||||||
高さ
高木 (10~30m)

|
花の性別
雌雄異株
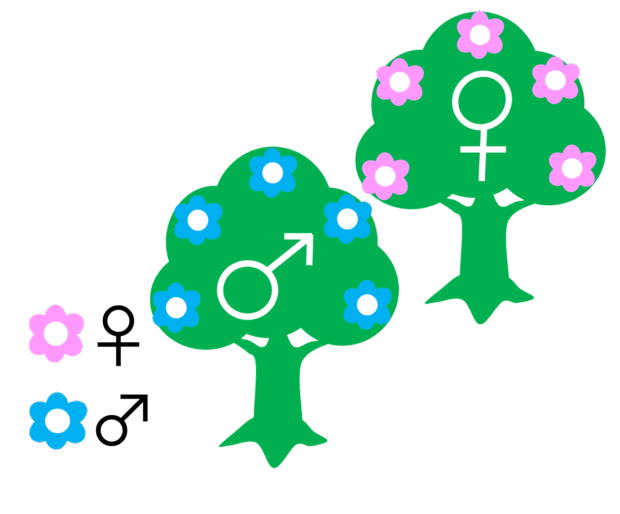
|
|||||||||||
分布原産地は中国・台湾・フィリピン。 日本には大正初期に渡来。 |
生息地- |
|||||||||||
分布原産地は中国・台湾・フィリピン。 日本には大正初期に渡来。 |
||||||||||||
生息地- |
||||||||||||
学名Pistacia chinensis |
||||||||||||
樹形
葉
葉は複葉(小さな葉が集まって一つの葉になっている葉)。 小さな葉は2枚ずつ同じところから出ていてきっちりした感じ。 これが楷書の文字に似ているということで、 カイノキという名前になったと言われています。
花
雌木と雄木があります。 葉が出ると同時に房になった小さな花を咲かせます。
実
真っ赤に熟します。 カイノキはピスタチオに近い仲間ですが食べられません。
幹・枝
縦に深い皺が入ります。
皺の入り方も枝の付き方も、 整然としてすっきりとして美しい。 さすが学問の木!
枝や葉などは防虫剤のような香りがします。
冬芽・葉痕
黒っぽく三角おにぎり型の冬芽
人との関わり
カイノキは学問の木として広く知られてはいましたが、 日本には大正初期に岡山県の閑谷学校、 東京都文京区の湯島聖堂、 栃木県の足利学校の三か所に初めて植えられました。 その木々の子孫が広まり、 全国で植えられるようになりました。
名前の由来
葉や枝の付き方がきれいに整っている様子が、 楷書という文字体をイメージさせるということで楷書の木→楷の木(カイノキ)となりました。 ランシンボク、 トネリバハゼノキなど他にも色々な呼び名があります。
関わりが深い生き物
実を食べにいろいろな野鳥がやって来ます。
トサカフトメイガの幼虫は、 カイノキの葉を糸でつづり集団で生活しています。 (虫の苦手な方は閲覧注意です。 )
タップすると詳細が見られます