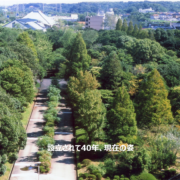高さ15m、 直径30㎝になります。

イヌシデ
実の形が四手のよう
特徴
小さな葉っぱを集めたような面白い形の実がなります。 神社でみる四手に似ていることから、 「シデ」という名前がつきました。
縁がギザギザの葉っぱと上品なストライプ柄の樹皮も個性的です。
みんなの投稿
以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。
 Peak Season
Peak Season Blossom
Blossom Leaf
Leaf Fruit
Fruit
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見頃 |

|

|
||||||||||
| 花 |

|

|
||||||||||
| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|
||||
| 実 |

|

|

|

|

|
|||||||
高さ
高木 (10~30m)

|
花の性別
雌雄同株
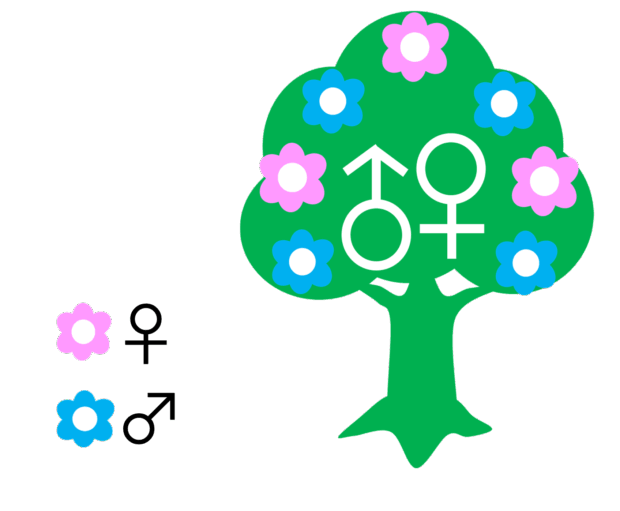
|
|||||||||||
分布北海道(南部)、 本州、 四国、 九州、 沖縄、 朝鮮半島南部 |
生息地山地や丘陵に多い |
|||||||||||
分布北海道(南部)、 本州、 四国、 九州、 沖縄、 朝鮮半島南部 |
||||||||||||
生息地山地や丘陵に多い |
||||||||||||
学名Carpinus tschonoskii |
||||||||||||
樹形
葉
互生(交互に葉がつくこと)です。
葉は卵を少し長くして尖らせたような形です。 縁に細かく鋭いギザギザがあります。
横向きに走る脈(側脈)が12~14対もあって目立ち、 まるで肋骨のようです。
花
早春、 黄褐色の花が垂れさがるように咲きます。
花が葉が出る前に咲くのは、 風によって雄花が花粉を運んでもらいやすくするためです。
実
小さな葉っぱを集めたような面白い形の実は、 夏から晩秋まで木についています。 最初は緑で、 秋に熟すと茶色くなります。 実を分解すると、 翼のついた種がでてきます。 冬がくるとこの種は風に飛ばされて遠くに運ばれます。
幹・枝
樹の幹はなめらかで、 白っぽい縦縞模様が目立つ独特の模様です。 この模様が好まれて庭木として植えられたりもします。 老木には浅い割れ目が入ります。
冬芽・葉痕
卵形で先端がややとがります。 鱗のような芽鱗(がりん、 芽をつつむうろこ状の皮)は12~14枚もあって、 きれいに並んでいます。
人との関わり
里山では活用されることはなく、 ほとんど伐採されてしまいましたが、 今人の手が入らなくなった森には沢山見られるようになりました。
名前の由来
シデは、 実が四手(しで)に似ているところからきています。 イヌは、 近い種類のクマシデやアカシデよりも特徴がない、 という意味です。
※四手(しで)...神前に捧げる玉串やしめ縄などにつける白い布や紙で作ったもの。
性格
木材が優秀というわけでもなく、 使えないからと山で残されて生き残ったタイプ。 ラッキーな木なのかもしれません。 ありふれた普通さが武器?決して優等生じゃなく、 葉のギザギザがでたらめな感じで、 勝手にシンパシーを感じています。
体験・遊び
まるでホップのような、 ミノムシのような果穂をほぐして、 種を観察しよう。 ほぐした種を高いところから落とすと、 くるくる回るかな?
関わりが深い生き物
枝先の冬芽に、 イヌシデメフクレフシというふっくらした虫こぶができることがあります。
タップすると詳細が見られます
見られる場所
執筆協力 : 「性格」「体験・遊び」岩谷美苗 執筆