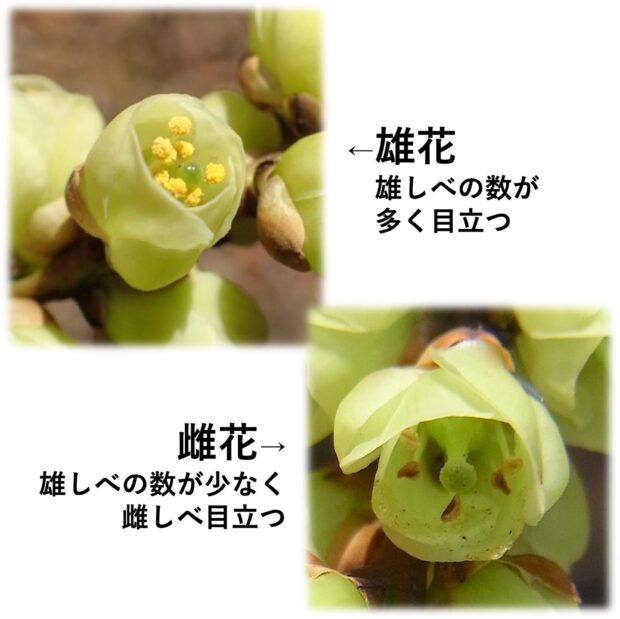2~4mほどになります。 雑木林や林の縁、 山地の道などの湿り気と日陰のある場所を好みます。 時に高さ7mになるものもあります。

キブシ
春を教えてくれる葡萄みたいな花
特徴
早春に咲くぶどうの房のような花は、 春のおとづれを教えてくれます。
夏から秋にみのる実も、 鈴なりでよく目立ちます。 この実はお歯黒を作るのに使われました。
みんなの投稿
以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。
 Peak Season
Peak Season Blossom
Blossom Leaf
Leaf Fruit
Fruit
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見頃 |

|

|
||||||||||
| 花 |

|

|
||||||||||
| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|
||||
| 実 |

|

|

|

|
||||||||
高さ
小高木 (5~10m)
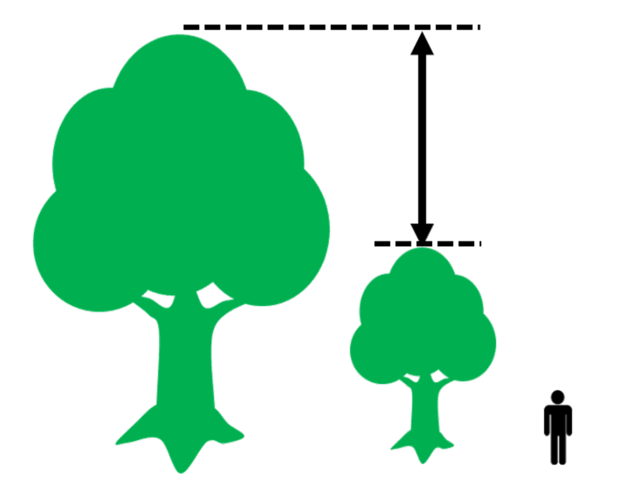
|
花の性別
雌雄異株
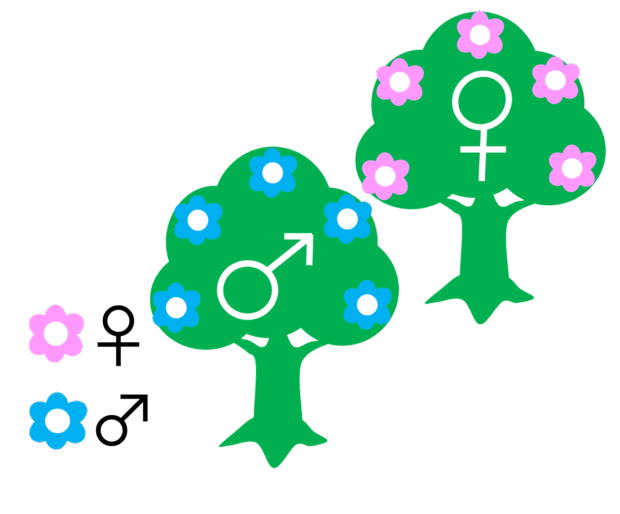
|
|||||||||||
分布北海道(西南部)、 本州、 四国、 九州 |
生息地やや湿り気のある日向地を好む |
|||||||||||
分布北海道(西南部)、 本州、 四国、 九州 |
||||||||||||
生息地やや湿り気のある日向地を好む |
||||||||||||
学名Stachyurus praecox |
||||||||||||
樹形
葉
葉の長さは6~12㎝。 楕円形または卵形で先がとがります。 縁にはギザギザがあります。
地域差が大きいです。 →このページ内の「その他の情報」の項目を参照
花
雄の木と雌の木があります。 葉が直前の3~4月頃、 枝先に房が伸び鐘形の花が房状に集まって咲きます。
小さな花が房状にあつまってつきます。 集雄花は淡い黄色で、 雌花は雌花より緑がかっていて地味な色をしています。
実
7~10月頃に実をつけます。 はじめは緑色ですが熟すと黄褐色、 最後は黒色になります。
幹・枝
赤褐色または暗い褐色です。 枝はその年に伸びた枝は緑色か、 赤みを帯びた緑色で、 毛がなく、 光沢があります。
冬芽・葉痕
先がとがり、 2~4個の鱗(芽鱗)に包まれています。 鱗には毛はなく、 赤褐色~暗褐色です。
人との関わり
昔は髄を灯篭の中心の柱(灯心)に、 果実に含まれるタンニンをお歯黒に使用していました。
名前の由来
果実をヌルデの虫こぶの五倍子(ぶし=お歯黒の際に使用される虫えい)の代用品としてしばしば使われるため、 木五倍子(きぶし)または豆五倍子(まめぶし)という和名が付いたと言われている。
その他の情報
キブシは日本固有種ですが、 さらに地域的な変異が多いのが特徴です。
ナンバンキブシ、 ハチジョウキブシ、 エノシマキブシは、 キブシの亜種とされています。
一方、 小笠原諸島の : ナガバキブシ(葉が厚く、 果実が大きい)は別の種とされています。
関わりが深い生き物
春早く咲く花には、 ミツバチ、 ヒラタアブ、 チョウ、 ガ、 甲虫・・・などいろいろな昆虫がやって来ます。
初夏~晩夏、 葉を巻いた揺籃(ゆりかご)があれば、 ウスモンオトシブミを探して見てください。
タップすると詳細が見られます