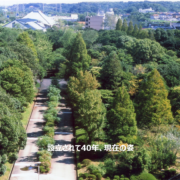成長すると丸いこんもりと丸い樹形になります。

マテバシイ
縄文人とともに日本の海辺に広がったドングリの木
特徴
大きな固いドングリが沢山みのります。 ドングリは食べられます。
元々沖縄・九州地方に生えていたものを、 縄文人が食料として広めたと言われています。
みんなの投稿
以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。
 Peak Season
Peak Season Blossom
Blossom Leaf
Leaf Fruit
Fruit
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見頃 |

|

|
||||||||||
| 花 |

|
|||||||||||
| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
| 実 |

|

|
||||||||||
高さ
高木 (10~30m)

|
花の性別
雌雄同株
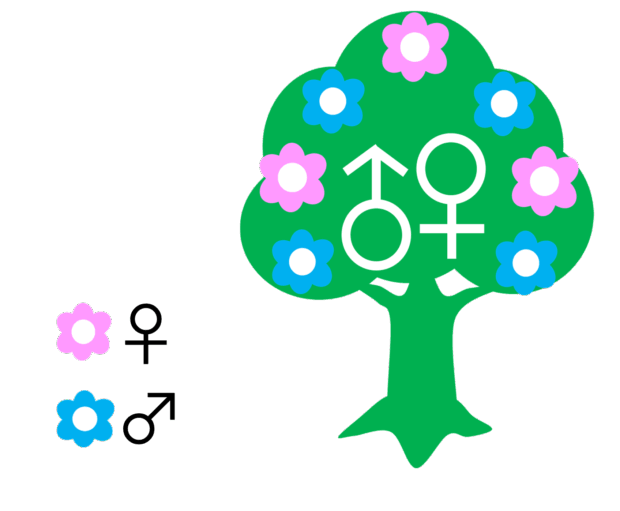
|
|||||||||||
分布本州、 四国、 九州、 沖縄。 古くから栽培され、 元の自生地は九州、 沖縄と言われています。 |
生息地沿海地に生えています。 |
|||||||||||
分布本州、 四国、 九州、 沖縄。 古くから栽培され、 元の自生地は九州、 沖縄と言われています。 |
||||||||||||
生息地沿海地に生えています。 |
||||||||||||
学名Lithocarpus edulis |
||||||||||||
樹形
葉
光沢のある厚手の葉っぱです。 ふちにはギザギザが全くありません。
花
雌花と雄花があります。 雄花は強い匂いを放って虫を呼んで受粉を助けてもらいます。
日本のドングリの花で一番咲くのが遅いです。
実
大きなドングリが毎年たくさん実ります。 初夏に花が咲いて翌年の秋に熟します。
お尻がくぼんでいるのが特徴。 硬くて虫に食われにくいです。
幹・枝
縦に白っぽい筋が入ります。
名前の由来
マテバシイ の名前の由来は、 実が椎の実(スダジイの実)のようにおいしくないことから、 「しばらく待てば椎(シイ)になる」と期待してマテバシイになったという説もあります。
その他の情報
<千葉県では海苔の養殖につかわれた>
マテバシイの木をきると根元から「ひこばえ」と呼ばれる新しい枝をたくさん伸ばします。
千葉県では、 これを海苔の養殖に使っていました。
関わりが深い生き物
ムラサキツバメ(チョウ)の幼虫はマテバシイの若葉を食べます。 幼虫は蜜を出し、 ボディガードとしてアリをやとっています。
アブラムシが枝にびっしりついており、 アブラムシの甘露(かんろ)を求めて、 スズメバチやアシナガバチなどがやってきます。
タップすると詳細が見られます