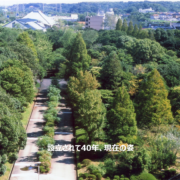高さは2~6mの低木。 自然だとよく枝分かれして葉が多く、 ずんぐりとした樹形になります。

マサキ
蝋細工のようなテカテカの葉っぱ
特徴
蝋細工のような明るい色合いの葉が一年中美しいので、 庭や生垣によく植えられます。 冬に熟す実はほんのりピンク色になってくると中から真っ赤な種が顔を出します。
自然では海の近くが大好きです。
みんなの投稿
以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。
 Peak Season
Peak Season Blossom
Blossom Leaf
Leaf Fruit
Fruit
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見頃 |

|

|

|

|

|
|||||||
| 花 |

|

|
||||||||||
| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
| 実 |

|

|

|
|||||||||
高さ
低木 (1〜5m)

|
花の性別
両性花

|
|||||||||||
分布日本(北海道 : 豊島半島〜琉球・南西諸島)、 朝鮮半島 |
生息地海岸付近の林内 |
|||||||||||
分布日本(北海道 : 豊島半島〜琉球・南西諸島)、 朝鮮半島 |
||||||||||||
生息地海岸付近の林内 |
||||||||||||
学名Euonymus japonicus |
||||||||||||
樹形
葉
光沢のある蝋細工のような葉っぱです。
花
初夏に黄緑色の花を咲かせます。
実
冬になると熟し、 中から赤いタネが出てきます。
幹・枝
樹皮は暗褐色で縦に浅い溝が出来ます。 若い枝は緑色で滑らかです。
冬芽・葉痕
冬芽は対生する葉のつけ根に背中合わせにつきます。 ぷっくりとしていて先がとがり、 たくさんの芽鱗がきっちりと並んでいます。 枝先の芽は1個だけのこともあれば、 両側にも2個ついて3個組のこともあります。
人との関わり
葉が密につき、 目隠しになるので生垣によく使われます。
アジア、 ヨーロッパ、 北アメリカなど世界各地で栽培されています。
名前の由来
葉が常緑でいつも葉があることから真青木(まさおき)からマサキになったと言われています。
関わりが深い生き物
花には、 ハナバチ、 ハエ、 甲虫などがやって来て、 受粉の手伝いをします。
ユウマダラエダシャクとミノウスバというガは、 住宅地のマサキの垣根でも見られます。
冬には、 シジュウカラ、 メジロ、 キツツキ類などの鳥が実を食べにやって来ます。
タップすると詳細が見られます