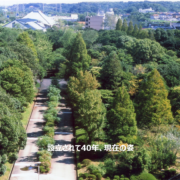高さ1.5~3mくらいになります。 中には5mくらいまで大きくなる木もあります。 枝はあまり分かれることはありませんが、 大きな葉っぱが目立つので遠くからでも見分けられます。

ヤツデ
ヤツデだけど切れ込みは八つじゃない?
特徴
大きく、 深くさける葉っぱは「天狗の羽団扇(はうちわ)」に例えられます。
手のひら状に八つに分かれるから八手(=ヤツデ)?と思われがちですが、 実際には切れ目の数は様々で、 7つや9つのように奇数に分かれていることが多いです。 寒い季節に咲く花は、 成虫で冬を過ごす生き物の数少ないレストランです。
みんなの投稿
以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。
 Peak Season
Peak Season Blossom
Blossom Leaf
Leaf Fruit
Fruit
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見頃 |

|

|

|

|
||||||||
| 花 |

|

|
||||||||||
| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
| 実 |

|

|
||||||||||
高さ
低木 (1〜5m)

|
花の性別
雌雄同株
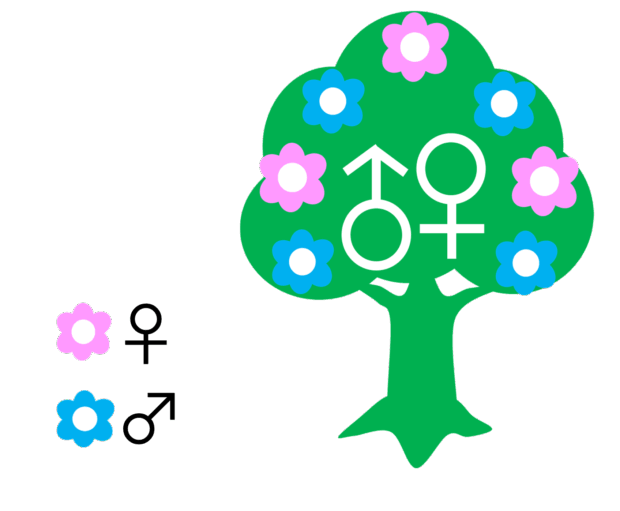
|
|||||||||||
分布日本(本州 : 茨城県以南、 四国 : 太平洋側、 九州 : 南部)東北地方南部での自生は栽培品から野生化したとさている。 |
生息地海岸に近い丘陵の林内 |
|||||||||||
分布日本(本州 : 茨城県以南、 四国 : 太平洋側、 九州 : 南部)東北地方南部での自生は栽培品から野生化したとさている。 |
||||||||||||
生息地海岸に近い丘陵の林内 |
||||||||||||
学名Fatsia japonica |
||||||||||||
樹形
葉
葉っぱの大きさは20~40㎝と大きく、 手の平のように5~9つに深くさけます。 葉の縁には、 あらいギザギザあります。
花
11~12月の冬の初めに、 枝の先に小さな白い花が集まって咲き、 かざりのポンポンのような球を作ります。
花の少ない寒い時期に咲くので、 たくさんの虫たちがやってきます。 花は「雄しべ先熟」といって最初に雄しべだけ熟し、 この時、 虫に花粉を運んでもらおうと蜜を出します。 花をよく見ると蜜がキラキラ光って見えます。 雄しべが花粉を出し終えると、 蜜も出なくなります。 その後、 雄しべと花びらが落ちて雌しべが熟すと、 また蜜を出して虫を待ちます。
雌性期の花は、 「毛が3本」のオバQ(古い?)の頭みたいで可愛いです!
実
5月ごろ、 枝先に黒っぽい紫色の実を付けます。
幹・枝
幹は灰色がかった色をしています。 葉っぱの付いたあとが半月の形で残ります。
冬芽・葉痕
夏に出来る花芽は黄緑色の葉っぱのようなカバーで守られています。 葉芽は枝先にツンツンとまとまって出て来ます。
人との関わり
自然でも多く生えますが、 日陰でも育つこと、 大きな葉がアクセントになるということで日本庭園によく植えられてきました。
名前の由来
漢字表記の「八手」の八は数が多いという意味があるといいます。 実際は葉の切れ込みは5〜11と様々です。
別名、 テングノハウチワともいわれます。
関わりが深い生き物
ヤツデの花は、 蜜がたっぷりあり、 虫たちのレストラン。 寒さに強いハエやハナアブなどがたくさん集まります。 スズメバチもやって来ますのでご注意を!
冬、 大きな葉の裏は小さな虫たちの越冬場所になります。 そっとめくって、 隠れている虫たちを探してみましょう。
実を食べに、 ヒヨドリなどの鳥がやって来ます。
タップすると詳細が見られます