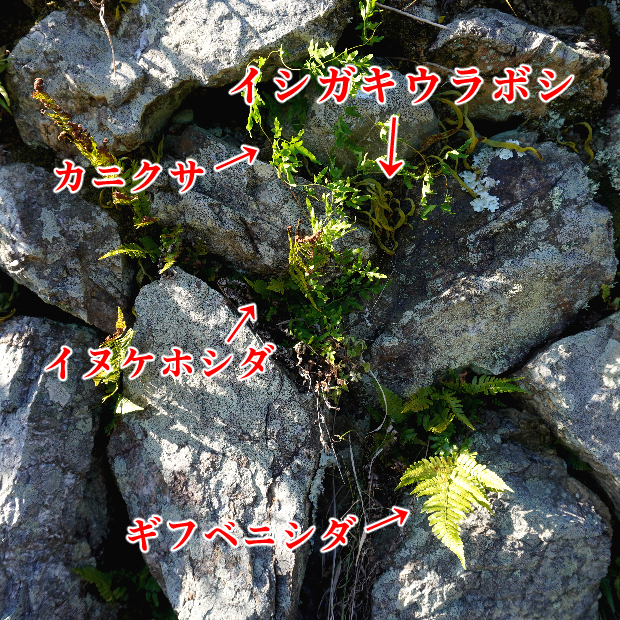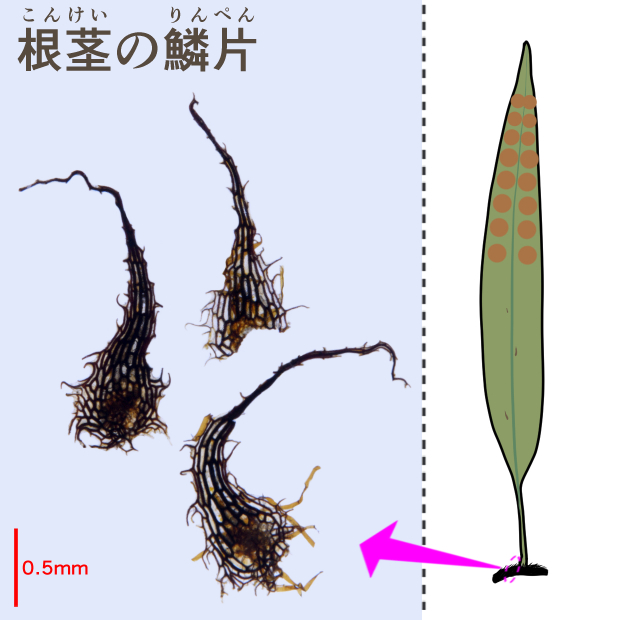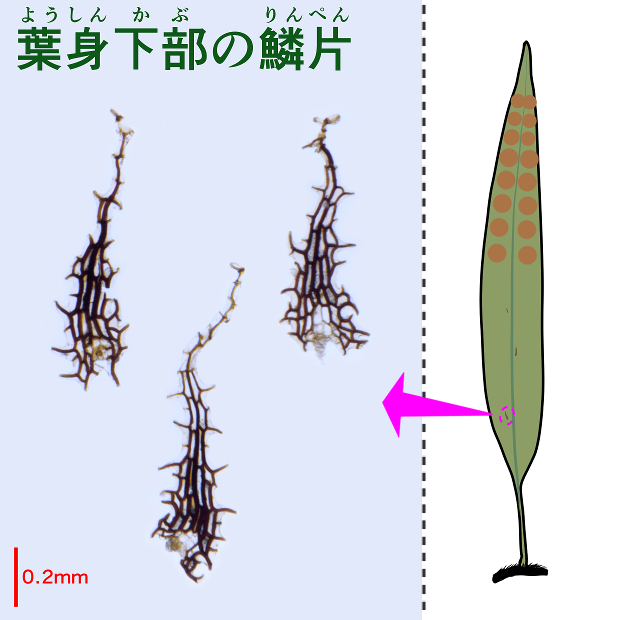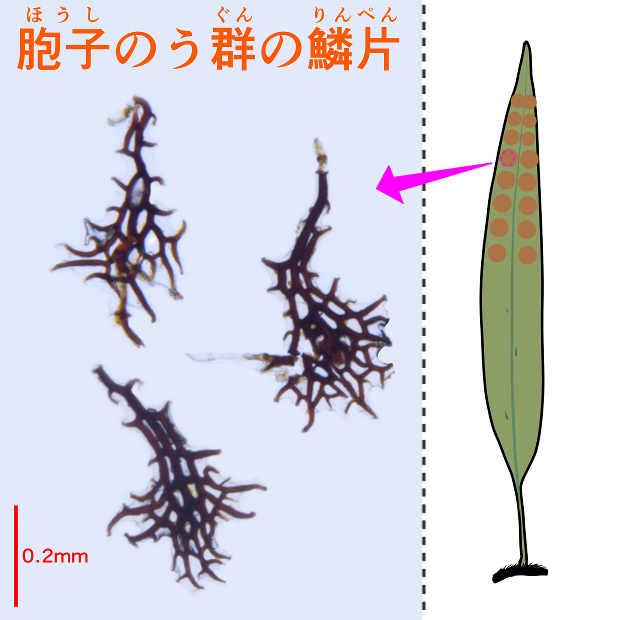-
石のすき間などに生える。
写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda
-
根茎をやや長くはって葉を出す。
写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda
-
表面。
ふつうツヤがなく明るい緑色で、 やわらかめ。
似た特徴のフジノキシノブよりは質が薄い。
写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda
-
葉裏。
胞子のう群は円形で、 フチと脈の中間につく。
写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda
-
若い胞子のう群。
三角形の鱗片に覆われる。
円形のノキシノブと大きく異なる特徴。
写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda
-
葉裏下部。
小さな長い三角形の鱗片が少しつく。
写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda
-
葉の下部。
葉柄までなだらかに細くなっていく。
葉柄は長くはっきりしている。
写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda
-
葉柄基部。
根茎には黒っぽい鱗片が多い。
写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda
-
暑さと乾きでしわくちゃになっている。
適した環境になると元に戻る。
写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda
-
人里の石垣で見られることが多い。
同じく人工的な場所を好むカニクサ、 イヌケホシダ、 ギフベニシダが混生。
写真 / 2024.7 三重県 S.Ikeda
-
根茎の鱗片。
全体が黒っぽく、 先が細く伸びる。
フチにいくつも長めの突起がある。
写真 / S.Ikeda
-
葉身下部の鱗片。
細長くて、 フチに突起が多い。
葉身上部にはほとんど鱗片が残っていなかった。
写真 / S.Ikeda
-
胞子のう群を覆う鱗片。
三角形状であまり細くならず、 フチに突起が多い。
ノキシノブ類の多くは円形。
写真 / S.Ikeda