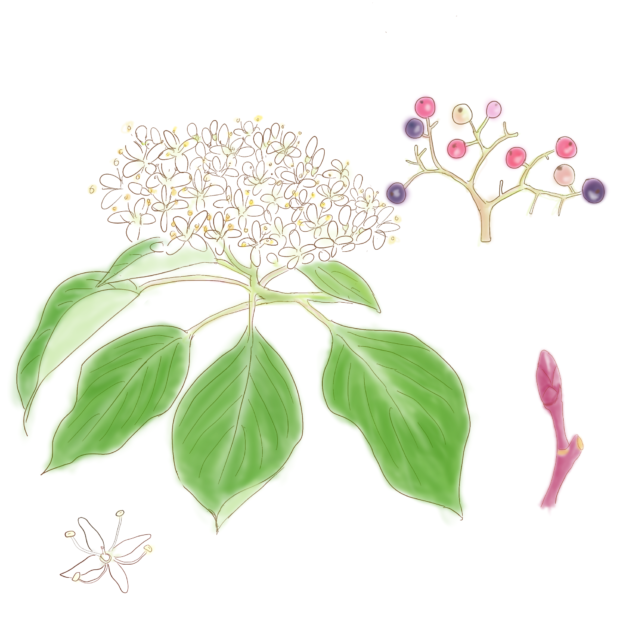枝の張り方が独特です。 長く太い横枝が突き出しており、 遠目から見ると特徴のある樹形になります。
一度この木の形を覚えると、 花の時期になると遠くから見ても木の形で分かるようになります。

ミズキ
早春に枝をきると水がしたたる
特徴
春先枝を折ると水が滴り落ちる、 そこからミズキという名前がつきました。
冬の赤い枝がとても綺麗で目立ちます。 お正月飾りの繭玉(まゆだま)を飾るのに使います。
みんなの投稿
以下の情報は、 関東地方を基準にしています。 エリアによって1ヶ月くらいの差があります。
 Peak Season
Peak Season Blossom
Blossom Leaf
Leaf Fruit
Fruit
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見頃 |

|

|
||||||||||
| 花 |

|

|
||||||||||
| 葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|
||||
高さ
高木 (10~30m)

|
花の性別
両性花

|
|||||||||||
分布北海道、 本州、 四国、 九州、 朝鮮半島、 中国、 台湾、 インドシナ、 ヒマラヤ。 |
生息地丘陵から山地、 水辺に多く生えます |
|||||||||||
分布北海道、 本州、 四国、 九州、 朝鮮半島、 中国、 台湾、 インドシナ、 ヒマラヤ。 |
||||||||||||
生息地丘陵から山地、 水辺に多く生えます |
||||||||||||
学名Cornus controversa . var. controversa |
||||||||||||
樹形
葉
枝に交互につきます。
柄が長く、 カーブした葉脈がよく目立ちます。
花
初夏に小さな花がたくさん集まって咲きます。
小さなコガネムシなどの虫が沢山やってきます。 それらの虫は、 花粉を食べつつ受粉の手伝いをしているのです。
実
はじめは赤く、 完全に熟すと黒くなります。 鳥がよく食べにきます。
幹・枝
成長した木の幹は、 網目模様になることが多いです。
冬、 横に張り出した枝は、 赤くきれいです。 この枝はお正月の繭玉を刺す枝として使われました。
冬芽・葉痕
赤い枝についた丸みのある濃い赤色の冬芽がよく目立ちます。
名前の由来
樹液が多く、 早春に枝を切ると水がしたたり落ちることから「ミズキ」という名前になりました。
関わりが深い生き物
上向きに咲く白い花には、 コガネムシの仲間など多くの昆虫がやってきます。
5~6月、 キアシドクガ(ガ)が、 ときに大発生することがあります。
ミズキの実は鳥たちのごちそう。 いろいろな鳥が好んでよく食べます。
タップすると詳細が見られます